-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2025年12月 日 月 火 水 木 金 土 « 11月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
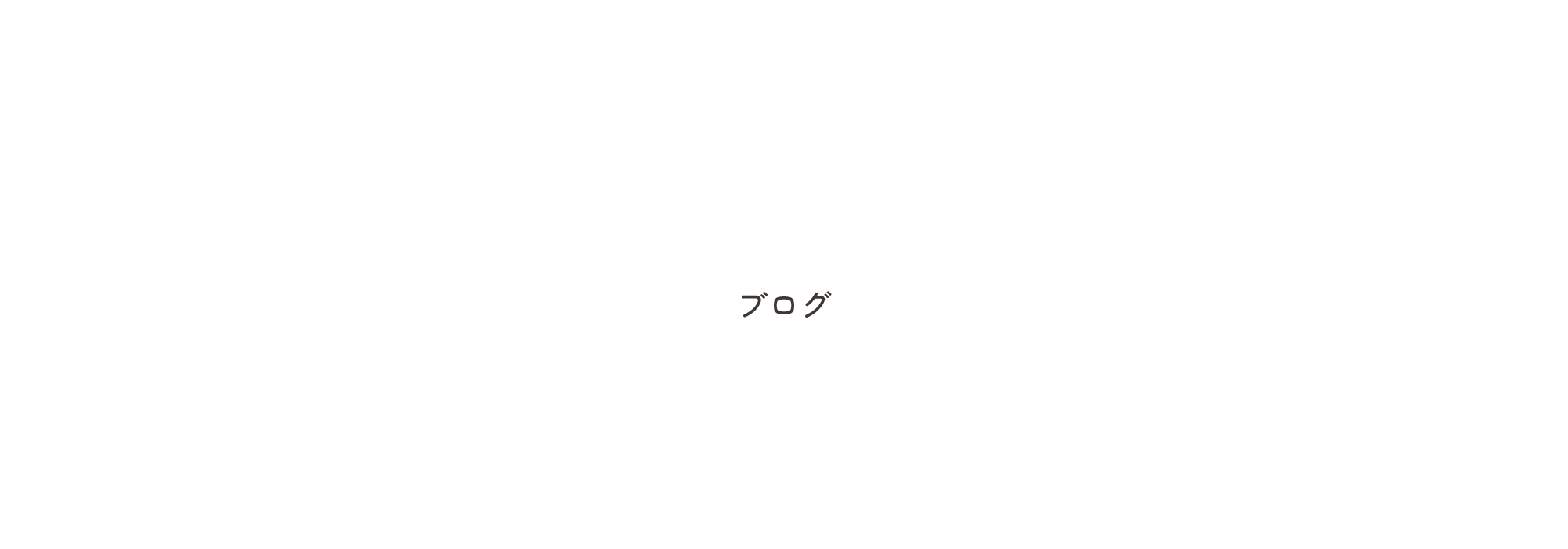
皆さんこんにちは!
株式会社マゴコロ、更新担当の中西です。
さて今回は
目次
感情の流れ:
否認 → 怒り → 取引 → 抑うつ → 受容
日によって行き来するのが自然な反応。
言葉がけのポイント
「そう感じるのは自然です」
「一緒に作戦を立てましょう」
比較の罠
「隣の家はできている」→ 家庭ごとに条件・支援体制が違うと説明する。
1️⃣ 目的共有:「“できることを増やす”を優先に」
2️⃣ 役割分担:家事・見守り・通院同行を具体的に割り振る
3️⃣ レスパイト計画:デイ・ショート・訪問看護など、使い時を決めておく
4️⃣ 連絡網の整備:昼/夜/緊急時の窓口を一本化
“話し合い=負担調整の時間”と位置づけることで、家族の安心感が増す。
| 家族の葛藤 | 対応・提案 |
|---|---|
| 「入浴は毎日!」論争 | 安全と体力を優先し、部分清拭+足浴を提案。 |
| 「自分がやるのが愛情」 | “やり方を整える=愛情”と再定義。用具・導線を省力化。 |
| 金銭不安 | 小額財布+レシート貼付で見える化。詐欺対策も併せて説明。 |
「“毎日完璧”より、“無理なく続くやり方”が安全です。
今日は足湯と清拭で温まって、明日入浴にしましょう。
記録を写真で共有して、うまくいった型を増やしますね。」
言葉+共有+振り返りで“成功体験”を可視化。
事実:休む家族ほど介護を長く続けられる。
選択肢:
・デイの短時間利用
・入浴のみ利用
・ショートステイ“半日”から始める
休むサイン:
怒りっぽい/眠れない/涙が出る → 「そろそろ休む合図」️
“休む=続けるための技術”として伝える。
金銭・鍵・通帳:
原則として触れない。受け渡しは第三者立ち会い。
ハラスメント対応:
複数訪問・記録・通報フローを事前に説明。
個人連絡先:
利用者・家族に渡さず、事業所を窓口に統一。
⚠️ 現場を守る仕組みが「継続支援」の土台になる。
介護疲れで口論が続いていたNさん一家
状況:入浴頻度をめぐり夫婦喧嘩が常態化。
介入:家族会議で週2全身浴+隔日清拭に合意。
→ 「できた日シール」で成功体験を可視化。
結果:口論が半減し、会話時間が増加。
「達成感の共有」が家族の雰囲気を変える。
☐ 家族の感情に“名前”をつけて返したか
☐ 役割・連絡網・レスパイトの3点セットを提案したか
☐ 金銭・鍵・通帳には触れない運用にしたか
☐ ハラスメント対応の窓口を周知したか
家族支援は「説得」ではなく「整えること」。
言葉 × 選択肢 × 休む仕組み を整えることで、
家族はもう一度“介護を続ける力”を取り戻します。
寄り添いとは、我慢を減らし、希望を見える形にすること。
皆さんこんにちは!
株式会社マゴコロ、更新担当の中西です。
さて今回は
SOAP・経過記録・引き継ぎの“型”
目次
| 要素 | 内容 | 記入例 |
|---|---|---|
| S(主観) | 利用者・家族の言葉をそのまま引用 | 「『今日は足が重い』と訴え」️ |
| O(客観) | 観察した事実・数値・時刻 | 「歩行速度低下、SpO₂ 96%、食事6割」 |
| A(評価) | SとOからの仮説 | 「疲労+軽度の脱水の可能性」 |
| P(計画) | 次の行動・方針 | 「白湯200ml、午後は外出控えめ。明日も歩行速度を確認」 |
ポイント:
誰が読んでも同じ行動が取れるよう、事実 → 判断 → 次の一手を明確に。
| NG表現 | OK表現 | 改善のポイント |
|---|---|---|
| 「部屋が汚い」 | 「床に洗濯物3点、廊下に紙パック2本」 | 状況を具体的に描写 |
| 「機嫌が悪い」 | 「声量が上がり『帰る』を5回発言」 | 主観を排除し、事実で表す |
| 「いつも通り」 | 「朝食:粥200g、味噌汁半分」 | 定量的に記録 |
判断語を避け、誰が読んでも同じ光景が浮かぶ“再現性のある記録”を意識。
〈時刻〉8:55 〈出来事〉入浴介助
〈観察〉立ちくらみ×1回(約30秒)
〈対応〉座位休息+白湯100ml
〈結果〉表情改善
〈次回〉入室前の水分声かけ、浴室マット増設検討
3行ルール
1️⃣ 今日起きたこと
2️⃣ なぜ(仮説)
3️⃣ 次回どうする
視認性UPの工夫:
タグ絵文字で定型句を見やすく(例:=入浴/=食事/=口腔ケア)。
❌ NG:「特になし」「いつも通り」
✅ OK:「昼食後に眠気強く、15時の散歩は短めに」「便秘傾向:最終排便8/20」
連絡先も明記
主治医 → 訪問看護 → ケアマネの優先順を統一。
| よくある問題 | 改善策 |
|---|---|
| 計画と記録のズレ (目標“掃除”なのに内容“会話”ばかり) |
ケア目標を生活目標に翻訳:「来客を迎えたい」など具体化。 |
| 同じ表現のコピペ | 食事量・歩行速度・表情・排泄などの時系列変化を観察。 |
| 個人情報の扱い | 必要最小限の記載+施錠・持ち出しルール徹底。 |
「今日は歩行速度が遅めで昼食は6割、白湯で改善。明日は入浴前に水分を先に取ります。」
✨ 1文の構成ポイント
数字(定量)
比較(変化)
次の一手(行動計画)
Before:「ふらつきあり」
After:「立ち上がり2回目でふらつき、椅子に手をつかない。夜間トイレ2回」
→ 足元灯+手すり設置を提案し、夜間転倒ゼロを実現。
☐ S/O/A/Pの順に書けたか
☐ 事実と解釈を分けたか(引用と数値)
☐ 次の一手(P)を書いたか
☐ 引き継ぎメモを未来志向で残したか
今日の記録から 判断語を3つ削除 し、
事実表現 に言い換えてみよう。
(例:「元気そう」→「会話時に笑顔・声量一定・歩行安定」)
良い記録は、“賢い現場”の証明。
誰が読んでも同じ対応ができる文章にすることで、
✅ 事故が減り
✅ 情報共有が速くなり
✅ ケアの質が継続的に上がる。
️ 記録は「作業」ではなく、チームの“思考の軌跡”です。
皆さんこんにちは!
株式会社マゴコロ、更新担当の中西です。
さて今回は
目次
評価軸:重大性(S)× 頻度(F)をマトリクスで分類。
例)
- S高 × F高:転倒(夜間トイレ)/誤薬(旧薬混入)
- S高 × F低:火災/誤嚥
- S低 × F高:軽微な打撲/小物紛失
方針:
リスクTop5を抽出し、資源を集中投下。
👉 対策例:手すり設置・照明改善・服薬管理仕組み化
1️⃣ 事実確認:呼吸・意識・出血の有無をチェックし、周囲の危険を除去。
2️⃣ 安全確保:体位・保温・安静を維持。必要に応じて 119通報。
3️⃣ 連絡:家族 → ケアマネ → 主治医/訪問看護(順序は事業所ルールで統一)。
4️⃣ 記録:事実と推測を分けて記入。
🕒 時刻/場所/状況/対応/結果を具体的に。
5️⃣ 共有:当日中にチーム全体へ報告し、再発防止を迅速に。
KPT法
– K(Keep):良かった点
- P(Problem):課題
- T(Try):次の改善策
5 Whys(なぜを5回)で真因を掘り下げる
> 例)転倒 → 夜間暗い → 足元灯なし → 設置していない理由は? → 費用/認知の問題 → レンタル提案+家族説明
アクション設定
👉 改善策には必ず「期限」と「責任者」をセットで。✅
| リスク領域 | 最低限の対策ポイント |
|---|---|
| 転倒 | 履物・段差・動線・手すり・夜間照明。歩行スピードと立ち上がり回数を観察。 |
| 誤嚥 | 姿勢・一口量・食形態・食事速度。食後30分は座位保持。 |
| 火災 | IH調理/自動消火装置/感知器設置。外出時は電源チェック表を活用。 |
| 金銭 | レシート貼付・代理受領ルール・財布の定位置化。 |
| 誤薬 💊 | 一包化・ラベル・保管場所固定・旧薬廃棄の徹底。 |
| 個人情報 | 書類の持ち出し最小化。施錠・シュレッダー徹底。 |
Kさん(夜間転倒)
👉 足元灯+ポータブルトイレ+ベッド高調整 → 夜間歩行ゼロに。
Lさん(誤嚥)
👉 食形態をムース化、“一口ごと嚥下確認”でむせ回数1/4に減少。
Mさん(金銭トラブル)
👉 レシート貼付+小額財布導入で家族の不安が解消。
整合性の確保:
計画書・記録・報告書の表現を統一。
ヒヤリハット集計:
月次で件数をグラフ化し、対策実施率も併記。📊
研修記録:
参加者/内容/所要時間/振り返りを記載して保存。
☐ Top5リスクを決定し、担当者と対策を明確化したか。
☐ 事故時の初動フローを掲示・周知したか。
☐ ヒヤリハットを月次で集計・KPTで議論したか。
☐ 記録書類の整合性を確認したか。
リスクは「なくす」ではなく「管理する」もの。
見える化 × チーム運用で、
在宅の安全と安心を底上げしましょう。
👥 共有・仕組み・継続こそ、事故ゼロへの最短ルートです。
皆さんこんにちは!
株式会社マゴコロ、更新担当の中西です。
さて今回は
目次
手指衛生(5つのタイミング) 🙌
① 訪問前
② 入室時
③ ケア前後
④ 体液接触後
⑤ 退出時
👉 アルコールが使えない汚れは「石けん+流水」で洗う。
個人防護具(PPE)
状況に応じて:手袋・マスク・エプロン・ゴーグルを選択。
咳エチケット
本人・家族にもティッシュ・マスクの使い方を共有。
| ケア場面 | 標準的な対応手順 |
|---|---|
| 入浴・清拭 | 手袋着用 → 終了後に手すりなど高頻度接触面を拭き取り。 |
| 排泄介助 | 手袋+エプロン。便汚染物は密閉袋に。トイレ清拭は上から下へ。 |
| 洗濯 | 手袋で取り扱い → 直接洗濯機へ。衣類をはたかない。乾燥まで実施。 |
| 清掃 | ドアノブ・手すり・スイッチなどを定期的に拭き掃除。 |
| 調理 | 生食材と器具を分ける。まな板・包丁は洗浄→乾燥を徹底。 |
換気・ゾーニング:出入りを最小にして空気を流す。
装備:使い捨て手袋・マスク・エプロン・ゴーグル(必要時)。
処理手順:
1️⃣ 外側から内側へペーパーで拭き取り。
2️⃣ 家庭用塩素系製品(表示濃度)で拭き取り。
3️⃣ 布類は密閉袋に入れ → 洗濯へ。
手指衛生:処理後はしっかり手洗い。
冬(インフルエンザ対策) ❄️
・加湿と換気のバランスをとる。
・加湿器の水替え・洗浄を忘れずに。
夏(食中毒・脱水対策) ☀️
・台所の拭き取り回数を増やす。
・飲水をこまめに声かけ。🥤
「消毒は“やりすぎ”も“やらなすぎ”も困ります。
手がよく触れる場所を毎日拭く、吐物は表示濃度で拭く、終わったら手洗い。
この3つだけを続けるのが一番効果的です。」
🌡️ 38℃以上の発熱 + 強い咳/息苦しさ/ぐったり感
🤢 激しい嘔吐・下痢・血便・意識変化
→ 主治医・訪問看護へ連絡。緊急時は 119通報。🏥
☐ 手指衛生のタイミング(前・後・接触後)を守ったか
☐ PPE(手袋・マスク・エプロン等)の使い分けができたか
☐ 高頻度接触面の拭き取りをルーティン化できたか
☐ 嘔吐物処理の流れを家族と共有できたか
「いつもの型」に落とし込むほど、ブレは減る。
標準予防策を 淡々と回す ことが最大の防御です。
流行期はほんの少しだけ強化、それが在宅の最適解。
🏠 日々の習慣が、感染ゼロのいちばんの近道です。